今年もレアゾンのエンジニアとして早期の活躍を図るべく、約2か月半に渡る新卒向けエンジニア研修を実施しました。昨年窪田さんが理想としていた“毎年次の代の新卒に運営主体を引き継いでいく”という流れを実現し、多くの2024新卒の方々が研修の企画運営に携わりました。 参加者数も昨年比1.5倍となったことで、規模感も各段にアップしています。また、2024新卒のデザイナーメンバーにもご協力いただきお揃いの研修用パーカーも作成し、運営・参加メンバー問わず、より一体感がある研修を生み出しています。 まずは、今回本研修全体のPMをしている新川さんに、今回の研修を作り上げていく中で、こだわったポイントや昨年からの変更点など、お話を伺いましたのでご覧いただけますと幸いです。 若手のうちから様々な業務へ携わることができることが改めてご理解いただける内容となっているかと思いますので、是非今後のキャリアなどにご参考くださいませ。
.jpg?width=516&height=516&fit=inside&format=webp&quality=90)
新川 悠斗
しんかわ ゆうと
menu事業本部 開発部 プロジェクトマネージャー
京都大学工学部理工化学科卒。就職活動を通じてIT業界に興味を持ち、エンジニア職でレアゾンの選考を受ける中でPMとしての適性を評価され、2024年に新卒でプロダクトマネージャーとして入社。
現在は、フードデリバリーサービス『menu』の配達員様向けプロダクトのPMとして開発チームを牽引し、ユーザー体験の向上と業務効率化に取り組んでいる。
また、昨年度の新卒エンジニア研修に参加し、プログラムの設計や育成の重要性に関心を持ったことをきっかけに、今年度は研修全体を統括するPMとして育成支援にも携わる。
今回、研修の企画運営に携わろうと思った理由は?
昨年度の新卒エンジニア研修に参加し、ハッカソンなどを通じて同期とのつながりが深まったことや、充実したカリキュラムから多くの学びを得たことが印象に残っています。一方で、与えられた内容をこなすことに集中してしまい、もう一歩踏み込んで自分で考え行動する経験が少なかったようにも感じました。
「優秀な人材ほど、環境によって伸び方が変わる」と考えており、受講生が早い段階から“自ら考えて動く”経験を積むことで、より力強く成長できると確信しています。もともと人材育成や組織づくりに関心があり、将来的にそういった分野に関わっていきたいという思いもあったため、今年度は研修PMとして運営に携わることを決めました。
.jpg?width=1832&height=1832&fit=inside&format=webp&quality=90)
昨年からレベルアップを図るにあたり意識したこととは?
今年の研修では、特に「自主性」をキーワードに、受講者・運営者双方の成長を促すことを意識して設計を行いました。
① 受講者の成長を促す「構造」の設計
昨年の研修に参加した際、カリキュラム自体は非常に充実していた一方で、受講生が受け身になりがちで、自ら主体的に学びを深めていく機会がやや不足していると感じました。 そこで今年は、受講者が自ら考え、動くことを前提にした構成に転換することを意識しました。たとえば、昨年は合同で行っていたWeb・ゲーム向けの研修を分割し、より応用的かつ実践的な内容に特化した講義設計とすることで、自ら選んだ領域で、より専門的な内容を学び、それをみんなの前で発表して、受講者たちが自発的に議論できるように促しています。
② 運営側の自主性を引き出すチームマネジメント
研修PMとして、自らが全てを管理するのではなく、「大枠のスケジュールや方針を定め、あとは各メンバーに任せる」というスタイルを取りました。 運営チーム内では、頼り頼られるフラットな関係性を築くことを意識し、それぞれの強みを活かして進めることで、運営側にとっても成長機会の多い研修となるよう設計しました。
③ 自主性の文化を根付かせる
今年の研修全体を通じて目指したのは、受け身ではなく、自ら選び・動く人を育てる土壌づくりです。これは受講者だけでなく、運営メンバーにとっても同様であり、「教える・設計する」という立場を通して、それぞれが主体的に動ける環境を整えることを重視しました。 昨年と比べて「自主性」というテーマをあらゆる面に浸透させた点が、今年の研修の最大の特徴です。
.jpg?width=1832&height=1832&fit=inside&format=webp&quality=90)
エンジニア研修全体スケジュール
| テーマ | 日数 |
|---|---|
| ①shell/OS | 1営業日 |
| ②Git | 1営業日 |
| ③アプリケーション基礎 | 1営業日 |
| ④SQL | 1営業日 |
| ⑤WEB or Game | 13営業日 |
| ⑥PM研修(PM座談会/ユーザー理解座談会) | 1営業日 |
| ⑦ネイティブアプリ研修 | 5営業日 |
| ⑧インフラ | 2営業日 |
| ⑨ハッカソン(最終日に最終発表会) | 16営業日 |
研修内容
①shell/OS
・OSの基本的な構造や役割についての概念的な理解から、日常的なトラブル対応やシステム操作に活かせる知識までを体系的に学習
・シェル(bash など)を用いた基本操作から、実務でも活用されるファイル操作・リダイレクト・プロセス管理・自動化などの一連の操作を実践
・OSやシェルの内部で実際に起きている処理を意識しながら、GUIでは得られない深い理解と操作スキルをハンズオンで習得
・エンジニアとして必要な「CUIの基礎体力」を身につけることで、上位レイヤーの技術にも応用できる基盤を構築
②Git
・Git/GitHubに関する概念的な部分から、実際にチームでGit/GitHubを使用する際に実務で行う一連の作業の流れまでを体験
・各コマンドの裏側で実際に起きている内部構造の深堀や、様々なパターンでのコンクリフトの解決方法などハンズオンを通して学習
・チーム開発で必要となるGitの多種多様な機能を理解
③アプリケーション基礎
・システムを構築する上で前提として知っておくべき「常識的なポイント」についての知識を体系的に伝える
・データの送受信と加工というシンプルな視点から、アプリケーションがどのように機能しているのかを理解
・データを扱うために必要な多様な技術領域を知り、より広い視野でシステムを捉える力を養う
・エンジニアとしてのキャリア形成についても併せて考えるきっかけとする
.jpg?width=1832&height=1832&fit=inside&format=webp&quality=90)
④SQL
・バックエンド研修の一環として、業務で必要とされるデータベースの基礎を体系的に学ぶ
・「データベースとは何か」「なぜ&いつ使うべきか」といった概念的な理解を深める
・基礎的なSQLを用い、現実的な課題に対してチームで協力しながら問題解決を行うハンズオンを実施
・実務でも頻出するデータベースへの負荷とその対策方法について、事例を交えて紹介
・トランザクションコントロール(ACID特性、コミット/ロールバックなど)についても扱い、安全なデータ操作の基本を習得
⑤WEB or Game
【WEBコース】
・フロントエンド・バックエンドの基本を講義形式で学び、最終的には「魔改造menuアプリ」を開発する実践プロジェクトに挑戦
【Gameコース】
・アクションゲームを作成できるレベルを目指し、実務で求められるゲーム開発スキルを習得
・企業でゲームを作るとはどういうことかもあわせて学ぶ
.jpg?width=1832&height=1832&fit=inside&format=webp&quality=90)
⑥Project Management研修(PM座談会/ユーザー理解座談会)
・実際にレアゾンで活躍しているPMや若手メンバーに集まっていただき、プロジェクトマネジメントやユーザー理解に関する座談会を実施
※本記事の後半で座談会の様子を簡単にご紹介します
⑦ネイティブアプリ研修
・Flutterを用いたスマートフォンアプリ開発を通じて、ネイティブアプリの作り方と特徴を体験的に学習
・開発からデプロイまでの流れを一通り実践することで、アプリケーション公開までの工程全体を理解
⑧インフラ
・インフラの基本的な役割と構成要素について学び、アプリケーションが稼働する土台を理解
・実際のプロジェクトではどのようにインフラが構築され、維持されているのかをケースベースで紹介
⑨ハッカソン
※次回記事で詳細をご紹介させていただきます!
ここで、『⑥Project Management』研修で実施した座談会を2種類ご覧ください。
https://drive.google.com/drive/folders/1TXBdswhrIwoS72hPCM02HdSFATWWzvSX
①PM座談会
会社という組織でエンジニアリングをするにはチームでの協力が必要不可欠であるということを学ぶために、実際にPMとして活躍している兼子さん・鈴木さん・保田さん・木村さんの4名に集まっていただき、“プロジェクトマネジメント”とはどんな職業で日々何を意識して働いているのか、そして、エンジニアとしてチームにジョインした新卒メンバーがPMの方々とどのように関わることが良いのか、お話いただきました。

兼子 英明
かねこ ひであき
株式会社アドレア 開発本部 PM
Web系のエンジニアを経験したのち、PMをメインにして7年目くらい。2024年9月に広告事業を担うレアゾングループの株式会社アドレアへ入社。現在は社内利用ツールにおけるシステム開発のPMを担当。

鈴木 貴也
すずき たかや
株式会社ルーデル ネイティブプロジェクト開発PM
ゲーム関連のフロントエンジニアやディレクターを経て、PMとして株式会社ルーデルへ入社。現在は既存タイトルや新規開発プロジェクトなどの案件を担当。

保田 雄太郎
やすだ ゆうたろう
menu株式会社 menu事業本部 クループロダクトPdM
2023年に新卒でバックエンドエンジニアとして入社。2024年にmenu事業部内のクループロダクトに携わり、バックエンドのリードエンジニアとして従事。現在はPdMとして引き続きクループロダクトを担当。
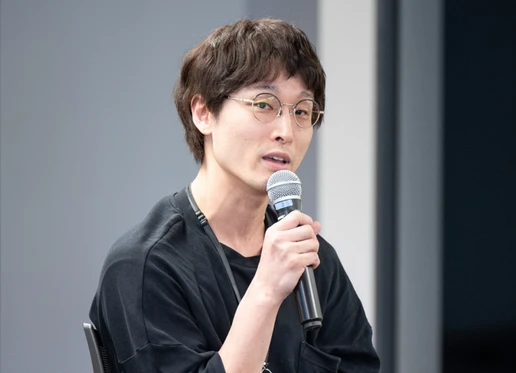
木村 祐章
きむら よしあき
株式会社レアゾン・ホールディングス 事業企画開発
フリーランスエンジニアを経てPM職種へ転向し、数々のプロジェクトを経験。2024年4月より新規事業であるペットIoTサービス『miruto』に携わり、PM/PdMとして従事。
<理想のPM像とは?>

PMという職種の定義は会社によってそれぞれですし、プロジェクトによってもやることは全く異なります。今の時代、AIも活用しながら全て一人で何でも作ってしまう人もいますが、せっかく企業に所属しているからこそダイナミックなことを実現したいので、時にはチームに各方面の専門家に加わっていただきます。その際、専門性が高い内容も多いので、PMとしてチームメンバー全員が共通言語でコミュニケーションを図ることができるように翻訳する必要があります。そう考えると、PMとは“一番コミュニケーションをする人”であると感じます。

PM業務では、目的に向かってどのようなアプローチをしてそのために何が必要なのかを考えて工程を管理することが重要だと考えています。また、実際にプロジェクトが進んで開発段階に入ると、PM業務としては余裕が出てくるので、そのタイミングで「何か漏れがないかな?」「問題は起きていないかな?」と気にしながら、適宜、細かいボールを拾います。PMを例えると、舵をきる船長でもあり細かいことでもなんでもする雑用係でもあると感じます。

兼子さんとニュアンスは似ていますが、PMとはプロジェクトの方向性を指し示す先導でもあり、各メンバーが作業の目的を見失わないように各工程の進捗状況を確認する潤滑油でもあると考えます。プロジェクトを円滑に進行していくためには、先頭を切って歩きつつ、細かいところにも目が届くような人材が必要だと思っています。
.jpg?width=1832&height=1832&fit=inside&format=webp&quality=90)
<PMの面白さ・やりがいは?>

事前に立てた戦略や方針がバチっとハマった瞬間です。PMの仕事は事前準備が8割程度占めていると思うので、都度方向性を調整して進め方を決めてチームメンバーに共有して「いいね!進めよう!」となり進んでいくプロジェクトは特に面白みを感じます。自分のPMでスピーディにプロダクト開発が出来た時は、素直に嬉しいなと思いますね。

私は基本的に問題は起きるものと考えているので、その上で問題が発生した際に迅速に着地まで持っていくことが出来た時は、やりがいを感じます。いくら事前準備を行ったとしても問題は付き物だと思うので、どんな手段を取って解決に導いていくかを考えることが楽しいです。

様々なプロフェッショナルな方と話しをすることが多いので、色々な技術や普通に生活していたら触れないジャンルの知識を勉強したり習得することができ、多様な人や価値観と間近で触れ合うことが出来ることが、PMの面白さです。様々な職種の人たちと触れる機会が多いポジションならではの魅力なのではないのでしょうか。

例えばプロダクトオーナーや承認者からGOサインが出た時や、方針が決まり開発に進む時など、意思決定がなされた瞬間は楽しいです。先述した通り、PMは物事を前に進める役割なので、前に進んでいる感覚があると何とも言えない達成感がありますね。
<プロダクトをどのように推進しているか?>

プロジェクトメンバーが目的を失わないように環境を整備していきながら、進捗が滞りそうなところを助けながら進行を促すようにしています。私向けの内容ではなくても、ある程度やり取りは把握しておくようにしていますし、兼子さんからお話があったように開発期間に入るとPMは少し業務が落ち着くので、いかにリスクを減らすか考える時間に充てています。

チームメンバーが最大のパフォーマンスを発揮できるような状況を作ることを心がけています。私自身はあえてあまり手を動かさないようにしており、エンジニアやデザイナーの方々が快適に仕事をできる環境を作るために、事前に決めるべきところは決めて情報共有も正確に行うように気を付けています。

「チーム全員で前に進めるんだ!」という気持ちを持つことを意識しています。結局手を動かすのはエンジニアやデザイナーの方々でありPM一人では何もできません。そのためには、良い成果を出していくという一体感がチーム全体にないと成功しないと思っています。1+1=2ではなく、1+1=2以上のアウトプットを生み出せると私は考えているので、N人集まったらN以上の働きができるような環境作りを必要としています。

とにかくチームで一番考えて一番話すことがプロジェクトを推進するには重要なことだと思います。どのようなプロジェクトのプロダクトも、最終的には会社で行う以上ビジネスに繋がるものであったり、何か目指しているゴールがあります。その目標を実現するために頑張り続けても、最後の最後に100%になることはないので、結果的に最後まで「本当にこれでいいのかな?」と考え続けながらプロジェクトを推進しています。
.jpg?width=1832&height=1832&fit=inside&format=webp&quality=90)
<今までの一番の成功 or 失敗体験を教えてください>

超BIG機能のリリース直前で問題が発覚し振り出しに戻ってしまった時のことは深く印象に残っています。『menu』のクルーチームで開発していた非常にインパクトが大きい機能があるのですが、いざリリースとなった時に、社内の各部署に悪影響が出てしまうことが発覚してしまい、結果的にやり直しとなってしまいました。エンジニアの方々を始め多くの人がリリースを楽しみにしてくれていたということもあり、モチベーションを下げてしまうことになったことは、個人的に一番失敗した経験です。

失敗でいうと各メンバーがそれぞれ少しずつ想定していたリリース時期に対して認識のズレがあり、結果的に大炎上してしまったことがあります。人はそれぞれ独自のバイアスを持っていると思うので、適宜認識合わせをしていくことの重要性を改めて感じました。
成功でいうと、ビジネスサイドから要望のあったリリース日は開発工数的に難しいと、PMとしては最初判断していたのですが、エンジニアの方々がプロジェクト自体にやりがいを感じてくれており全力で取り組んでいただいたおかげで、結果要望通りにリリースできたことは、嬉しかったです。

ゲームをリリースした後に漏れが発生したことに気付き、アプリの更新が必要という状況になってしまいました。それからは、関係各所にお願いをしてそれぞれのスケジュールを切って動いていただき、最終的にQAチームへチェックいただいている段階で、やはりデータの更新だけで解決できるという話に落ち着きました。無事リリースは出来たのですが、みなさんが協力してくれたからこそだと考えています。私の中では失敗した出来事ではありますが、同時に改めて周囲への感謝の気持ちが芽生えました。

前職で開発の受託案件を受けていたお客様でプロダクト開発の案件に関わったことがあるので、その時に失敗を経験しました。事前準備や企業調べも不十分だったことも原因で、進めれば進めるほど悪循環で納期にも間に合わず、結果的に契約を切られてしまうということがありました。この経験は私の中では学びになっていて、今のPM業務に活かされていると思います。
<エンジニア・デザイナーへ期待すること>

プロジェクトで気になることはどんなことでも良いので共有してほしいと考えています。チームによっては異なると思うのですが、PMはあくまで管理をするという役割なので、実際に開発などプロダクトに近い距離にいるメンバーでないと気が付けないこともあります。その気付きは私たちPMではなかなかキャッチが難しいこともあるので、とにかく違和感など感じた際は共有していただけると、非常に助かります。

一人で悩みを抱え込まず、周囲に相談してほしいです。実際、個人では解決できない問題も多いと思いますし、チームだからこそ解決できることもたくさんあります。まずは何か悩みが出てきたら、みんなを巻き込んで解決に持っていければ良いという気持ちで業務へ臨んでいただければと思います。

自分の領域に線引きせずどんどん意見を言ってほしいと、私は感じます。誰が担当しても良い仕事はたくさんある気がしており、自分の役割に縛られず色々な角度から意見してもらうことで、よりよいプロダクト開発の実現に繋がると思っています。チーム全員、対等なパートナーであるべきだと考えているので、是非提案・反論していただきたいです!

関わるプロジェクトに対して自分のやりがいや価値を認識して、自分ごととして関わってほしいと思います。やりがいを見つけることで自分が今やるべきことを見出せて、必然的にプロジェクトや事業全体を俯瞰して捉えることができますし、その方が楽しく仕事へ取り組むことが出来るのではないかと考えています。
.jpg?width=1832&height=1832&fit=inside&format=webp&quality=90)
②ユーザー理解座談会
昨年同様、様々な事業/ポジションでご活躍されている若手メンバーの皆様にお話を伺いました。

間嶋 健太
まじま けんた
ソーシャルゲーム事業部 運営部 ゲームプランナー
新卒で飛び込み営業を経験し、転職を経てmenu株式会社へ入社。最初は『menu』の店舗開拓営業を経験し、社内FA制度を利用してソーシャルゲーム事業部へ異動。現在は既存タイトル海外版の運営責任者として、売上の最大化を図るべく、キャンペーンやイベント企画などへ従事
※単独インタビューはこちら

川田 真生
かわた まお
miruto事業部 事業開発
社会人1年目でメディアレップ事業を立ち上げ売却。新卒2年目に株式会社レアゾン・ホールディングスへ入社し、2024年4月に株式会社newtとしてペットテック事業を子会社化。現在は社会人5年目。

大橋 薫
おおはし かおる
menu事業本部 クルー運営部 事業開発
2023年5月に新卒で株式会社レアゾン・ホールディングスへ入社し、現在2年目。フードテック事業にて配達品質の維持を目的としたオペレーション設計と管理業務に加え、配達リソース確保の戦略策定業務へ従事。2025年4月にクループロダクトのビジネスリーダーへ就任。

山田 梨加子
やまだ りかこ
プロダクト開発本部 新規事業部 マーケティング
入社時エンジニアとしてバックエンドの開発へ従事。入社3か月後に、よりユーザーに近いところで仕事をしたいという想いから、マーケティングへ転向。現在は、新規事業のマーケティングリーダーを担当。
<どのような目的でユーザー理解を実施しているのか?>

売上の最大化を図るために実施しています。私自身も1ユーザーとしてゲームをプレイしていますし、プレイすることでユーザー心理を理解することが出来ます。また、第三者意見のヒアリングも欠かさず行っており、定期的にユーザーの意見は拾うように心がけています。

より多くの人々に購入してもらうようなプロダクトを作るためです。ユーザーといっても色々なタイプの人がいるので、可能な限り多くの方々へヒアリングを実施しています。時には直接会ってインタビューさせていただくこともありますね。

中長期の戦略策定のためです。継続的に配達の品質担保を図るためには、クルーの方々がどのような心情で配達をしていているのか、理解する必要があります。定期的なクルーへのヒアリングは怠らず、日々改善に向けて施策を検討しています。

私は新規事業のプロダクトへ従事しているので、そもそも使ってもらえるアプリかどうか、市場調査を兼ねて将来ユーザーになりそうな人たちに向けてヒアリングを行っています。まだリリースしているプロダクトではないので、ある程度目星を付けた上でインタビューを実施しています。
.jpg?width=1832&height=1832&fit=inside&format=webp&quality=90)
<どのようなアプローチでユーザー理解を実施しましたか?>

ユーザーに近づくことができるアプローチ、つまり一次情報を取得できることは全て実施しました。具体的には、先述した通りユーザーへの直接インタビューや、保護猫活動、動物病院でのアルバイトなど、少しでもユーザーがいそうと感じたフィールドには積極的に足を運んでいました。

実際にクルーの業務を体験することが一番理解が深まったと思います。その他にも、クルーの方々へアンケートやインタビューの実施、時にはSNSを駆使したり、直撃取材も行い、生の声を拾いにいくこともあります。

大橋さんと似ていますが、私も実際にユーザーとしてゲームをプレイすることが、理解を深めるアプローチの近道だと感じます。また、アンケートなどを通してユーザーの声を聞いたり、分析ツールを用いてユーザーの動向を把握しています。

アンバサダーとして協力してくれている方が複数いるのですが、その方々ととにかく多くのコミュニケーションを取ることを意識しています。必ずしも全員のモチベーションが高いわけではないので、様々なターゲット層にヒアリングを行うことで、ユーザーが求めるプロダクトを作ることが出来ると考えています。
<ユーザー理解を通して得た知見とは?その知見はどのような施策に繋がりましたか?>

実際のクルーの業務や意見を把握したことで、本来ターゲットにすべきユーザー像の理解を深めることが出来ました。その結果、クルーが使用するアプリ内で配達中でも活動を記録/確認できる機能の実装へ繋がりました。

人にはモチベーションの転換や分岐が存在することを知りました。そのため、アプリ内のバッジやランキングなどを導入することで、可能な限りモチベーションを維持し続けてもらえるような工夫をしました。

実際に猫も飼い始め、毎日トイレを掃除することの大変さを肌で感じました。その大変さをいかに軽減できるか考え、自動トイレのレンタルサービスを開始しました。私自身も利用していますが、このサービスのありがたみを感じています。

直接ユーザーの声を聞いたことで、コア層のほとんどが日本版のゲームをプレイしていることが分かりました。私は海外版のゲームを担当しているので、運用を日本版に追いつかせる動きを取ることで、海外版でもコア層を獲得できるような流れを作りました。
.jpg?width=1832&height=1832&fit=inside&format=webp&quality=90)
<ユーザー理解の難しさとは?そしてどのように克服しましたか?>

私自身まだまだユーザーのことは30%程度しか理解できていないと感じます。理解度を高めるためには、日々自分でもサービスを使い続け、ユーザーになりきることが重要だと感じます。

担当タイトルをプレイするだけではユーザー心理全体を理解することは中々難しいと感じます。そのため、プレイをするだけではなく分析ツールを用いることで実際の数字の動きを把握し、ネクストアクションを検討しやすくなりました。

配達員開始時、当社サービスを選んだ(他社ではなくmenu)理由の超絶深堀をインタビューを通して行うことで、当社のサービスを使ってくださっている配達員の方の心情を理解しにいっています。

フィードバックが多くあり本質を見失いがちになることもあります。そうならないためには、アプリの使用頻度・使い方でユーザーを分類しフィードバックを整理することで、どんなプロダクトを作るべきなのか解像度が上がりました。
<ユーザー理解の手法や知見を社内でどのように共有していますか?また、組織的な取り組みはある?>

分析ツールを用いることで、誰でも担当タイトルの数字の動きを見ることができるようにしています。また、タイトル責任者間で各タイトルで行った施策、得られた知見や結果、それ対して次回どんなアプローチをとるか、デイリーでレポートを共有しています。

個人では時間を作ってユーザー理解の本を読んだりしています。やっぱりクルーの気持ちを理解するためには配達員をするのが一番早いので、チームの人たちには最初にまずは配達員の業務を体験してもらうようにしています。

一次情報が全てだと思うので、あえて組織内で知見を共有することはしていません。組織的な取り組みでいうと、出来るだけ実体験ありきでサービスに触れてほしいと思っているので、結果的に今は猫を飼ったことがある人が集まってきていますね。

今年は新卒2年目のデザイナーメンバーの協力もあり、研修用のロゴ入りパーカーも作成しました。それにより研修運営メンバーの結束力は更に深まり、研修内容も重厚になりハッカソンも全体的にレベルアップしています。
.jpg?width=1832&height=1832&fit=inside&format=webp&quality=90)
次回は、その一段階レベルアップしたハッカソンの様子をお見せできたらと考えておりますので引き続きお楽しみに!
.jpg?width=1832&height=1832&fit=inside&format=webp&quality=90)


